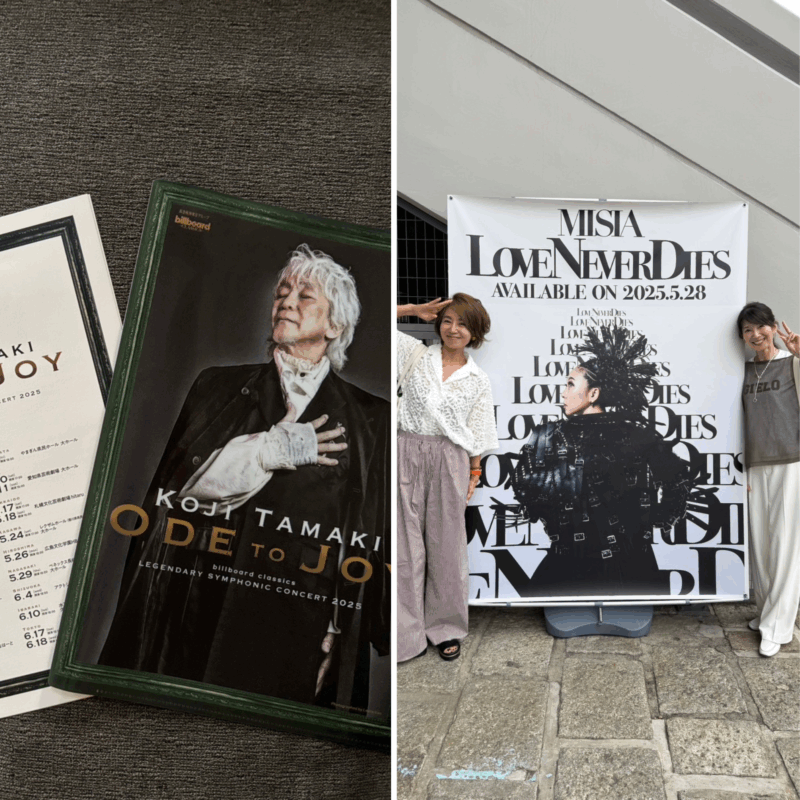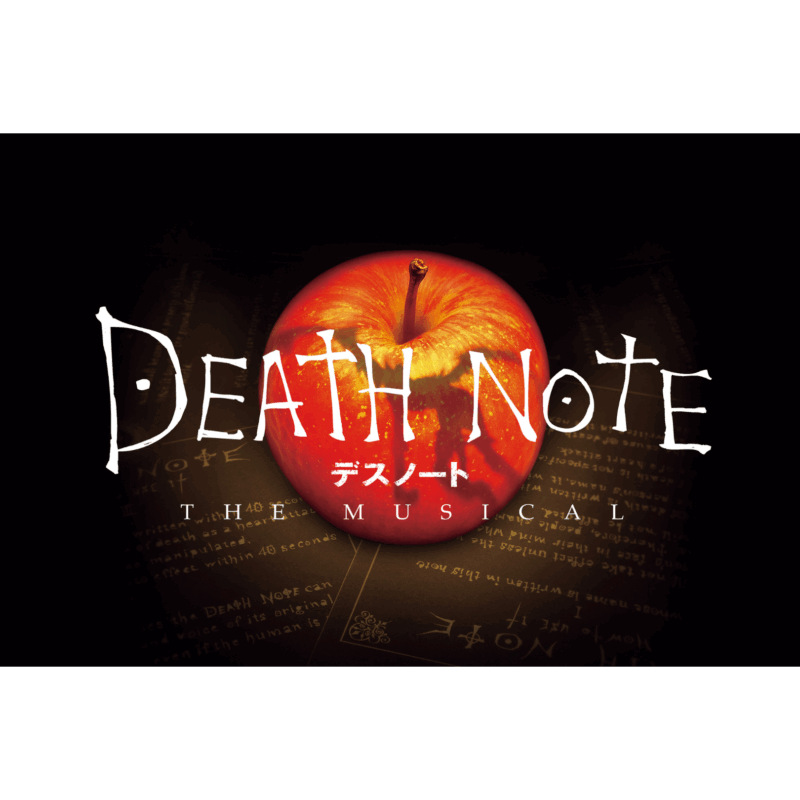10月17日東京・新宿の109シネマズプレミアム新宿にて、ユーミンこと松任谷由実さんが11月18日にリリースする自身40枚目のオリジナルアルバム『Wormhole / Yumi AraI』の完成を記念した『先行試聴会&トークライブ』を開催しました。なんとこのアルバムの楽曲の歌声はAIによって生み出されたユーミンの歌声でつくられているんです。旧姓の荒井由実時代から現在に至るまでのボーカルトラックを「Synthesizer V」に学習させ、再構築した歌声は「新しいのに懐かしい」と話題沸騰中。楽器の音と同様に「第3の声」も1つの素材として落とし込んで音楽をつくる。そんな新時代の先駆けに挑んだユーミンの思いが語られました。今回素敵なあの人編集部は試聴会&トークイベントに潜入! 気になるイベントの様子をレポートします。
目次
トークライブにユーミンが登場
この日、MCを務める制作プロデューサーの団野健さんの案内でユーミンがステージに登壇しました。この日は、スタッズがあしらわれたシースルー袖のミニのワンピースにシルバーのベルトでウエストマーク。ラメのタイツにスタッズをリンクさせたショートブーツを合わせた全身ブラックのコーディネートで登場。まさにユーミンたる抜群のスタイルと美脚に目を奪われました。
――今日は、久々に手ごたえのある作品が出来たということで、AIを取り入れた新たな挑戦もあるのでご本人からお話をして頂きたいなと我々が提案してこのイベントを開催させて頂くことになったのですが、完成して今の率直な気持ちを教えてください。
ユーミン:目下リハーサルの真っ最中で、このアルバムをこの肉体に落とし込むのに先週までどうしたらいいんだろうという状態だったんですけど、数日前にストーンと体に入りまして「AIと共生出来た」という手ごたえがこの試聴会に間に合いました。
――AIでつくったボーカルラインを、この後11月17日から始まる「FORUM8 presents 松任谷由実THE WORMHOLE TOUR 2025-26」のツアーで生でライブをするために、もう一回体に戻す作業ということですよね。大変苦労されていましたね。
ユーミン:はい。特に松任谷正隆がすごい時間をかけてタペストリーをつくるように、コラージュするようにボーカルトラックをいじってました。
――AIの使用から転じて「Wormhole」という異次元を繋ぐトンネルという意味を持つタイトルになりました。これは松任谷正隆さんが考えたとのことですが、最初聞いたときはどういう印象を持たれましたか?
ユーミン:能天気にアルバムをつくるのではなくテーマを設定してちゃんとみんなに届くようなものをということで、温度感としては「Wormhole」は合っていたんですが、さらに何かないかなと迷っているうちに、『Wormhole / Yumi AraI』という「Synthesizer V」を表すワードを松任谷が見つけてきまして、「知ってるか?お前の旧姓ってARAI AとIに囲まれてるんだぞ」と。ダジャレのような、でもおぼしめしのように名前を変えたのでそれで腑に落ちました。
――時空みたいなものをテーマにするのは今に始まったことではなく、『REINCARNATION』『昨晩お会いしましょう』『VOYAGER』と、割と時空をテーマにしたアルバムを出されてますが、そういった興味はいつごろからあったんですか?
ユーミン:子供の頃から普通に持ってましたね。アルバムをつくるにしたがって言語化したりビジュアル化したりしながらやって来て『REINCARNATION』が典型的だと思います。誰も知らない言葉で難しいんじゃないかなと思ったけれど、出したら通ってしまったので、今回も通るんじゃないかなと。
――今回AIを使うにあたり過去のボーカルトラックを学習させて第3の松任谷由実の声をつくったということなんですけど、被験者になったということも言えますね?
ユーミン:そうですね。もうここまでやってきたんだから次の扉を開けるためには、そこまでやっていいんじゃないかと。覚悟みたいなものも持ちました。
――曲づくりに関してですが、デビューされたときは自分で歌う想定ではなく「作曲家志望」だったと。そういう点で初期原点回帰されたそうですね。
ユーミン:今回は誰が歌うということを取り払って、特に作曲家として自由につくりました。そういう初期衝動が戻ってきたのをすごく感じて、(長年)ここまでやってきて初期衝動が起こることは自分でもすごいことだなと思っています。
――具体的に曲づくりに関してどういうところが確実に変化がありましたか?
ユーミン:キーレンジから自由になったということと、パッセージというかメロディの流れも自由になったと思います。
――由実さんの曲と言えば転調ですよね。
ユーミン:それも戻ってきて、特に「烏揚羽」という曲は、つくりながら入りこんじゃって「これは発明だぞ」と思って興奮しました。興奮してたらプロデューサーから「これだと出口のない曲だからサビをつくったほうがいい」といわれてそこを足したりもしたんですけど(笑)
――「中央フリーウェイ」とかも割と近いですよね?
ユーミン:そうですね、あれは転調によって帰結するので。
――実際レコーディングでは、由実さんが歌ったものをデータ化して複雑なことをやってるわけですが、先ほどお話に出た自分のフィジカルを鍛える必要があったと。
ユーミン:まずはボイトレで内声の震えというのを消すようにして。考えてみたら荒井由実のときのノンビブラートに直したんですが、それと全く同じではないですがVと混ざるように、共生するため地味なトレーニングを続けました。
――今回作詞作曲には結果的にAIは使わなかったですけども、作詞をChatGPTでトライしましたよね。
ユーミン:「岩礁のきらめき」という曲のサビからスタートするんですが、そこの部分は決めておいてバースに戻るところの文字数を読ませて、ChatGPTに「あなたは松任谷由実です」って前提でつくらせたら、自分では全く興味のない内容になってしまって。というのは一度手を染めていることなので、何か新鮮味がないんですよ。創作って自分にとっての衝撃が次のフレーズを持って来るので、置きに行くようなことはやっても意味が無いなと思いました。これが人だとしたら人の心も動かせないというのをその時点で感じたので、「人の心を動かすのは人にしか出来ない」という確信を得ました。
――そのあと、宮沢賢治風にとか夏目漱石風にとかもやって面白かったですね。
ユーミン:宮沢賢治のほうは「あれ?これいいかも」「使えるかも」ということが出てきて、それは多分私がすごく宮沢賢治が好きだからその手触りが出てきたもので。でもね、結果使いませんでした。これも私の見解なんだけど、日本語ってとくに行間とか、間とかそれが音律と一緒になったときその隙間にたくさん情報があるんですね。それをAIはまだ学習出来ないと思います。
――逆にAIと生身の人間の境界線が実感できたと?
ユーミン:はい。実感出来ました。よりAIと共生できるという。自分が無くなってしまったら飲み込まれてしまうんで、自分がしっかり強くあることがAIと共生できることだと思います。
――由実さんは自分の性格をご自身でどう分析されてますか?
ユーミン:そうですね、すごくきちんとしているところと、同じだけいい加減なところが両極にあります。
――それはちょっと「Wormhole」的? 違う次元の自分みたいな。
ユーミン:ずっと自分の中に「中二病」を飼ってるんですよ。私がスーパー中学生だとしたら松任谷正隆はスーパー小学生で(笑) スーパー中学生時代に自分の中でアンビバレント(相反する感情が併存していること)なものや色々な性格が培われたかなと思います。
――多重人格みたいな、いろんな自分がいるみたいなことも言えますか?
ユーミン:それはでも、きっとみなさんそうだと思うんですよ。(私は)わかりやすい職業だから、ステージに立っているときの自分とソングライティングしているときの自分と、家事をしているときの自分と全部違うということを説明しやすくもあり。ステージ上ではママチャリで買い物に行ってる自分のことは考えてないですが(笑) でも曲をつくってるときとかには日常が入り込むときはありますし、すごい日常生活で逃避のように音楽がきますね。
――家事って言うリアルな事象というか行為、創作は空想で無意識の中のもの。これは地続きになるんでしょうか?
ユーミン:説明が難しいですけど、シームレスなところもあります。
――このアルバムにそのシームレスな感覚が影響したところはありますか?
ユーミン:手ざわりで、さっきも触れましたが能天気は嫌だと思うんですね。毎朝新聞を読んだり雑誌を読んだりするんですけど、そこでの世の中の温度感みたいなものは入っているから作品にも反映されると思います。
――このアルバム、一言で表すとどんなアルバムでしょう?
ユーミン:キャリアを重ねてきたからこそテクノロジーにも会えて、今までのエッセンスをすべて注ぎ込むことが出来た私の最高傑作です!