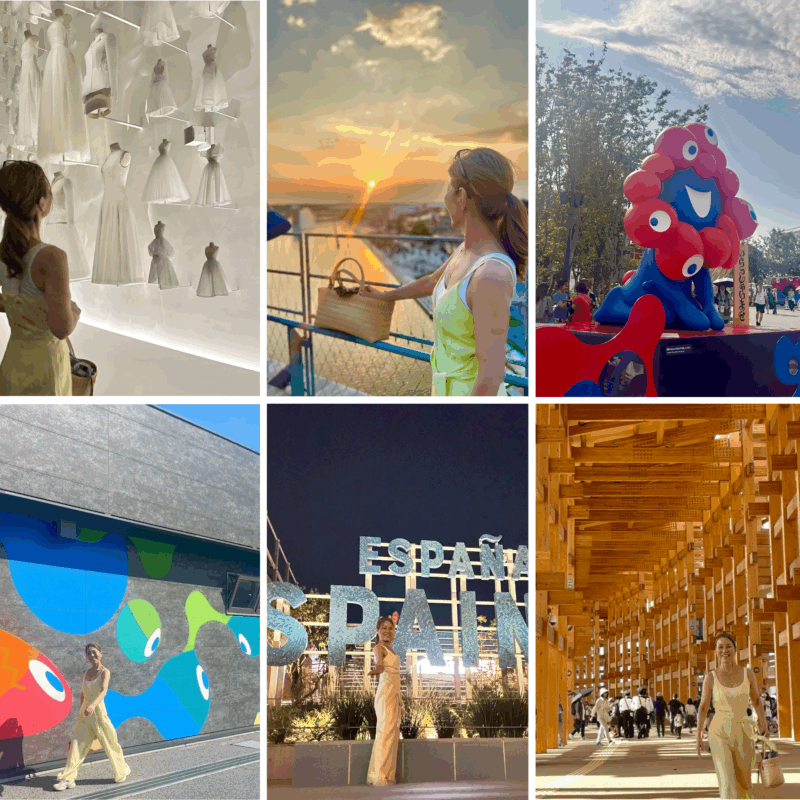近年、日本各地で国際的なビエンナーレ、トリエンナーレが数多く開催され、注目を集めています。街や地域そのものが現代美術の展示会場となる国際芸術祭の醍醐味とはどんなところにあるのでしょう?そんなビギナーのために、『ARTnews JAPAN』 編集長である名古摩耶さんが、現代美術の楽しみ方、そして、広大な会場から見たい作品を発見する方法をナビゲートします。
美術館を飛び出した大胆で自由な展示が芸術祭の醍醐味
「ビエンナーレ」「トリエンナーレ」と呼ばれる国際芸術祭がいま世界各国で盛んに行われています。ビエンナーレとは2年に1度を、トリエンナーレは3年に1度を意味するイタリア語。世界最古の国際芸術祭ヴェネチアビエンナーレに倣って、2~3年ごとに開催される芸術祭を指す言葉として定着しました。
「通常、美術館やギャラリーでは空間演出や装飾をなるべく排し、主役である“美術作品”そのものを引き立たせます。しかし地域と結びついた芸術祭では、その土地の文化や歴史、記憶、地政学といった関連性をより重視します。アーティストが地域の住民と協働しながら、開催地の地域性に基づいた新作を制作することもありますし、展示場所も野外や歴史的建造物や商店など、その土地の営みを感じさせる空間が選ばれることが多い。 国際的な芸術祭の醍醐味は、そこにあると言っていいでしょう。そうした試みは、作品の普遍性を生み、アートによって世界規模の社会課題を気づかせてくれることにもつながります」(名古摩耶さん※以下同)
名古さんが語る社会的な課題のひとつに「ヒューマンライツ=人権」があります。たとえば、私たちの世代は西洋圏の白人男性を中心にした美術史を学んできました。が、近年の国際芸術祭では、その偏りを修正しようとする機運が高まっています。
「2022年のヴェネチアビエンナーレは象徴的でした。男性アーティストに偏り過ぎていたジェンダーバランスを変えていこうと、女性あるいはジェンダー・ノンコンフォーミング(従来のジェンダー規範に当てはまらない人)のアーティストが参加者の90%を占めたのです。その結果、世界のアートシーンから大きな注目と高い評価を得て大成功をおさめました。2024年のテーマは『Foreigner Everywhere=どこにでもいる外国人』。移民や人種、そしてジェンダーやセクシュアリティを含む周縁化された人々をめぐる格差や問題を表現しています。現在、世界で起きている紛争などにも関わるセンシティブな課題を包括する力が、現代美術にはあります」
どこにでも外国人がいるということは、誰もが外国人であり、異質な存在であり得るということ。参加アーティストには、先住民のルーツを持つ作家も多くピックアップされました。アートが社会政治的な問題とより密接に関係している時代を迎えたと言えるかもしれません。ただ、アートはそうしたマクロな視点だけでなく、個人的な千葉国際芸術祭あいち鑑賞にも影響を与えます。
「なんらかの孤独や生き辛さを感じている人がアートに触れることで、同じ気持ちを抱えている人は地球の遠い場所にも存在していて、言葉を超えた表現として発信していると知ることができる。そして、勇気づけられ励さまされるきっかけになるかもしれません。それは本当に有意義なことです」